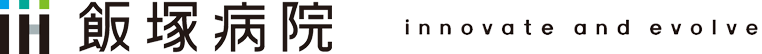飯塚病院 TQM活動報告
| 第30回(2022年) 第26回(2017年)~ |
第25回(2016年) 第21回(2012年)~ |
第20回(2011年) 第16回(2007年)~ |
第15回(2006年) 第11回(2002年)~ |
第10回(2001年) 第6回(1997年)~ |
第5回(1996年) 第1回(1994年)~ |
| 第33回(2025年) | 第32回(2024年) | 第31回(2023年) |
| No | 部署 | テーマ | 受賞 |
| サークル名 | テーマ選定理由 | ||
| 1 | E4救急・HCU | 意思決定支援の充実による看護の質の向上 | お客様賞 |
| E4救急・HCU timeless ~意思決定支援忘れているようじゃ無理か。意思決定支援はね、参加しとかないと~ |
救急・HCU病棟は重症患者が多く、患者や家族が意思決定する機会が多い。しかし、スタッフが意思決定支援に積極的に参加できていない。患者の意思決定に看護師が参加することで、今まで以上に患者に関心を寄せることができ、看護の質も向上すると考える。そのため、看護師が意思決定支援に参加できるように取り組みたい。 | ||
| 2 | 総合診療科外来(11B) ・救命救急センター |
ERと連携し総合診療科で入院する重症化リスクの高い(NEWs5点以上)患者の外来滞在時間を短縮する | |
| 飯塚病院には「救急」と 「総診」がある |
総合診療科は、転院搬送を含め複合疾患の患者に対応している。そのため、著明なバイタルサイン異常は認めなくても、重症化リスクが高く、迅速に適切な環境で診療が開始されることが望ましい。だが、システム・構造上、検査等に時間を要し、外来滞在時間が長い。外来看護師は長時間患者対応が必要となり、患者・家族も身体的・精神的負担につながっている。これらの課題を解決するため、ERとの連携を進めたい。 | ||
| 3 | 北第八病棟 | 保清を行いたい | |
| 保清で心の温もり伝え隊 | 北8階病棟は終末期やADL全介助の患者、人工呼吸器装着中の患者や、処置、緊急入院、COVID-19に追われる毎日である。保清を行いたいが、介護福祉士やe-nurseなど配置がなく、看護師だけで行う時間確保が困難な状態である。「保清をしたいけど時間がない」という強い思いを抱えている看護師も多くいる。保清を行い、患者のリラックスした表情を見ることが出来れば、看護師のやりがいやモチベーションの向上にも繋がると考えた。そのため、日勤帯に保清を実施出来る体勢を整える方法を考えたいと思った。 | ||
| 4 | 北第七病棟 | 患者のADL(日常生活活動)に左右されない充実した保清の提供! | |
| N7 保清向上委員会 | 保清は看護師の重要な業務であるが、現場では、患者や家族から保清に対して要望を受けることがあり、十分な保清を行えていないというジレンマがあります。ADLが低下していればいるほど、保清は必要となりますが、その分時間も人手(マンパワー)も必要となります。今回のTQM活動を通して、保清が十分に出来ていないという問題について原因を突き止め、効果的な対策を通じて、保清が充実できる体制を構築していきたい! | ||
| 5 | 中央第四病棟 | 心臓カテーテル検査室の連絡業務の効率化を図る | |
| カテ室の知らない世界 ~2nd season~ |
年間約1750例の治療・検査が⾏われている心臓カテ-テル室が病棟に併設されており、終日緊急対応をしている。予約リストは予約時間などの内容の確認しかできず、搬入時間の調整は看護師が症例中から電話連絡で行い、室外で進捗状況が把握できない事で医師のPHSへの緊急性の低い電話対応で業務の中断を余儀なくされている。 そこで、連絡に関連した業務中断を改善することで、患者の傍で集中して看護業務が実践できると考えた。 | ||
| 6 | 南2A病棟 ・血液浄化センター ・臨床工学部 |
血液浄化センターにおける入院透析患者の受け入れ人数の見直し | |
| 透析患者、 はいよろこんで!!! |
入院透析患者数の増加に伴い、病棟透析室が満床になることがある。 当院は、急性期病院としての役割があり、患者の受け入れ体制を整えておく必要がある。今回、血液浄化センターと臨床工学部を含む3部署で患者のスムーズな受け入れ体制を整え、患者に対して安全で質の高い透析治療を提供したい。満床状態の解決により、新規入院患者の増加につながり、急性期病院としての役割を果たすことで、地域医療の貢献につなげたいと考える。 | ||
| 7 | リハビリテーション部 | リハビリ添書の作業時間の短縮と質の向上 | 審査員特別賞 |
| それゆけ!!リハパンマン!! ~添書が辛くて 力が出ないよ~ |
添書は1件あたりの基準時間は20分であるが、40分以上かかっているのが現状である。書類業務が業務時間を圧迫することは患者の診療時間にも影響を与えるだけではなく、スタッフの残業時間の増加にもつながる重要な課題である。また、添書に必要な内容が記載されているかどうかは、転院したのちの患者様へのシームレスで質の高いリハビリの提供に重要である。そこで、今回のテーマを添書の作成の作業時間の短縮と質の向上とした。 | ||
| 8 | 中央第六病棟 | 症状緩和が迅速にできる体制づくり ~ハートをつけて病室でお待ちしています~ | 最優秀賞 |
| まゆこワールド★ | 緩和ケア病棟では治療が困難になっても過ごしたい過ごし方ができるケアを目標としている。飯塚病院中長期計画の中で重要課題である健全経営に貢献する為に6床増床・一般・救急からの退室も強化し、可逆的な治療も積極的に実施するようになった。特に重症者の対応やその他の業務が重なる事で患者が必要としているケアに十分な時間が確保出来ないため、テーマを選定した。 | ||
| 9 | 薬剤部 | 薬剤師による病棟業務の拡充 | 優秀賞 |
| 業務の鉄人 | 薬剤部では1日の業務時間の半日を調剤室業務、残りの半日を病棟業務に充てている。昨年のTQMでは調剤室業務の応援体制を構築した。しかしさらなる人員減少により薬剤師の病棟業務時間の確保が困難となっている。病棟業務時間の減少によって情報収集の時間や患者への介入機会が減ることが予想される。限られた時間の中で病棟業務を行うために薬剤師による病棟業務を拡充させる必要があり、今回このテーマを選定した。 | ||
| 10 | 南3B病棟 | 認知症ケア充実に向けた体制構築 | |
| もっとあなたの 笑顔に愛たい♡ |
超高齢社会に伴い、認知症患者が増加している。自部署でも入院患者の7割以上が70歳以上の高齢者であり、認知症を患った患者が増加している。現在、患者の尊厳を守るため、身体拘束除去に向けた取り組みを行っておりスタッフの意識も変化してきている。身体拘束を除去するだけでなく、日内リズムを整え、離床時間を拡大することで、認知症患者がその人らしく過ごせるような体制を構築していきたい。 | ||
| 11 | 中央検査部 ・感染管理センター |
血液培養検査における検査前プロセスの適正化 | 最優秀賞 |
| はいよろこんで ~血培サポートします~ |
血液培養検査(血培)は血流感染症診療に必要不可欠な検査で、敗血症や菌血症、感染性心内膜炎など各種感染症の診断目的に実施されることが多い。適正な検査結果を得るためには採取のタイミング、採取量、消毒を含む採取手技、採取後検体の取り扱いなどの「検査前プロセス」が重要である。当院においてこのプロセスは多くのスタッフが関わるプロセスであるが、血培採取をたまにしか行わない部署も比較的多く、手技に対する不安の声も聞かれている。手技の不良等による常在菌の混入も一定の割合で認められており、誤った治療に繋がるリスクを孕んでいる。血培における検査前プロセスを適正化し、適正な治療に繋がる検査結果の提供に寄与したい。 | ||
| 12 | 西二階病棟 | 身体拘束の削減 | |
| 身体拘束しない こっちの検討 ~はいよろこんで~ |
西2階病棟は、超高齢の認知症患者が多い内科系混合病棟です。せん妄、ルート類の自己抜去、転倒転落リスクの高い患者等に対して身体拘束を必要とする場面が多々あります。セル看護提供方式導入後、患者のそばにいる事が増え、身体拘束30%削減に成功しました。しかし業務の状況でその場を離れる場面も多く身体拘束を0にできない現状です。診療報酬や倫理的側面からも、積極的な身体拘束の削減に取り組みたくこのテーマを選定しました。 | ||
| 13 | 東第四病棟 | 入退院における患者の待ち時間削減 | 優秀賞 お客様賞 |
| 入院?はいよろこんで! | 2024年度病院全体での病床稼働率は85.3%の中、東4階病棟は104%、平均在院日数8.4日、回転率3.8%と、入退院の多い病棟である。9時~10時は看護業務が集中し、退院の患者や家族を10時以降まで待たせ、更に入院における患者の待機時間も発生している。また、退院後のベッドメイキングが集中し、看護補助者の負担も大きい。退院を円滑にし、スムーズな入院を実現することで、患者の待ち時間を削減し患者価値の向上を目指したい。 | ||
| 14 | 医療福祉室 | 外来相談における、対応者の心的負担の軽減 | 審査員特別賞 |
| 三代目医療福祉侍 | 医療福祉室では外来患者に対し輪番制で日々対応している。突発的な依頼が大半で依頼の内容は緊急度の高い入院支援や在宅医療の導入、社会背景が複雑で他機関との連携を要するもの等多岐にわたる。患者・家族の待機時間もあり早急な対応や質の高い対応を求められ対応者の心的負担が高い現状がある。何故心的負担を感じるのか、原因を見極め、それを軽減するための方法等を追求するため取り組むこととした。 | ||
| 15 | 西三階病棟 | 患者の物品紛失件数を削減する | |
| 財サン!無くサン! 安シン 西3(ニシサン)! |
西3階病棟では、認知症や精神疾患のある患者が多く、物品管理が困難である。看護師は管理を担っているが、部屋移動や徘徊により紛失が多発し、物を探す時間が増えている。物品管理を見直し、効率化を図ることで、紛失を減らし、看護師が患者の傍でケアができる環境を整えたいと考える。 | ||
| 16 | 中央放射線部 | 51Aで受付したX線撮影検査(レントゲン)における患者滞在時間の短縮 | |
| Time less project ~待たせるようじゃ無理か、 待ち時間はね、減らさないと~ |
X線撮影検査で51Aに来た患者は、受付→検査待ち→検査実施→画像確認→次の予定へのご案内と進む。今回はこの一連に要する時間を患者滞在時間とすることにした。現状ではこの患者滞在時間が、様々な要因により延びることがあり、患者進捗が遅滞し、患者自身の負担にも影響している。今回の活動では、この患者滞在時間に着目し、短縮を目指すことで、病院全体としての患者経験価値を高め、まごころ医療の実践につながると考えた。 | ||
| 17 | 歯科衛生室 | 1日の業務を見える化し、無理無駄をなくして、残業をなくす | |
| みんな歯っぴぃ | 日によって患者数の変動があり、予約患者も初診患者も多く、診察までにかなりの待ち時間を要している。十分な診察時間が確保できていない。時間内に仕事が終わらず残業になり、スタッフも疲弊している。 |
| No | 部署 | テーマ | 受賞 |
| サークル名 | テーマ選定理由 | ||
| 1 | 東第七病棟 | 残業せずに帰ろう | |
| 東七階物語~第一章~ | 日勤・ロング日勤・夜勤ともに定時に退勤できてない現状がある。その中でもスタッフより、ロング日勤帯に、OPが終了する医師から指示オーダや処方オーダがあり定時で終わらない業務量を抱えている為、退勤時間が遅くなっていると意見が上がった。また、ロング日勤者の残業することが常態化し、モチベーションが下がり疲弊感が増している。そこで、ロング日勤者が定時に退勤できるように日勤帯、ロング帯の働く環境を整備する事で仕事の効率化を図りたいと考えた。 | ||
| 2 | 南3A病棟 | 糖尿病教育患者において、入院1週間以内に退院目標を明確化する | |
| DMさん、いらっしゃ~い! | 糖尿病患者では、慢性疾患看護として生活指導が重要となってくる。しかし、生活指導につなげる為の患者の目標の明確化ができていない。VSMを作成し、要因として現在行っている情報収集は職種別に異なる手順で行っており、重複している内容は多い事、指導内容の統一性・継続性に欠ける事等があげられた。そこで今回情報収集の見直しと仕組み作りを行い、患者目標の明確化を充実させるべくテーマ選定を行った。 | ||
| 3 | 南1A病棟 | ブロックカンファレンスが定刻に開始できる為の業務改善 | |
| 今日、どう?協働 | 南1A病棟では、全介助でのケアの必要な患者が多く在院している為、朝は清拭業務が占める労力、時間の割合が大きい。その中で、10時30分からのブロックカンファレンスが定刻に開始できず、その後の業務もタイムスケジュールから逸脱してしまい、業務が終わらない現状にスタッフは疲弊している。定刻開始できない要因を調査、分析し、多職種と協働してタイムスケジュールが遵守できるように業務の効率化を図りたい。 | ||
| 4 | 西一階病棟 | 入院受け業務の効率化 | |
| めんどうはごめんどう | 精神科の入院受けは、入院形態や患者の状態、隔離室への入室対応や危険物の確認など、独自性があり時間を要する場合がある。当科独自の入院に関する資料はH26年から改訂されておらず、スタッフによって説明内容や入院受けにかかる時間に差が生じている。入院受けの業務内容にムダを感じているスタッフも多く、入院受けの内容と方法を見直すことで、患者や家族へより良い看護提供、スタッフの業務負担の軽減が可能ではないかと考えた。 | ||
| 5 | 中央手術室 | 術後の経静脈的自己調節鎮痛ポンプの適正量を決める | 審査員特別賞 |
| 新しい鎮痛のリーダーズ | 手術後の患者は、点滴から自己にて痛み止め投与ができるようPCAを使用しているが、使い切れずに残ったPCAは手術室へ返却される。PCAの残量が発生することで、病棟看護師が手術室に返却しにくる業務の手間や薬剤師の麻薬処理に時間を要している。また薬液を破棄することでコストの無駄も発生している。これらのことから患者に適した術後鎮痛をおこなうことでPCAの返却個数・返却残量を減らす取り組みを行う。 | ||
| 6 | 救急フィールド(ER、ICU、H2救急、E4救急・HCU) | 救急フィールド内における補完体制の充実 | |
| えりことゆかいな仲間たちTHE FINAL | 今までの活動の中でも、応援体制に取り組むことはあった。適材適所に人員を配置したとしても、質が担保されていなければ、患者に適正医療が提供できない。そのため配置だけではなく質向上にも取り組む。また救急フィールドは、それぞれ部署の特性があり、即時対応には看護師のスキルに限界があり、不安を抱えている。質を担保しつつ、補完体制を整えられる仕組み作りをしたい。 | ||
| 7 | がん集学治療センター | ポート自己抜針(Pt)が可能なレジメンで、対象患者を選別しポート自己抜針(Pt)導入方法を検討する | 最優秀賞 お客様賞 |
| Brush Up Chemo Life | 近年、インフューザーポンプを使用しての治療が増加している。治療の流れはCVポートから穿刺し、化学療法を行ないインフューザーポンプを装着し帰宅、46時間後に来院しポート抜針される。体調が悪い、遠方であるなど患者・家族の通院の負担の声や、看護師もポート抜針の処置に時間を要しており、看護業務が圧迫されている。TQM活動で患者のポート抜針の来院負担と、看護師業務の負担を軽減したいと考えた。 | ||
| 8 | ICU | 注射に関連した無駄な業務を削減 | |
| あなたの注射を数えましょう~Let's Reduce~ | ICUに入室する患者は状態が不安定な為、注射オーダー数が多い現状にある。そのため看護師は勤務交代時の注射合わせに時間を要する。状態が安定しているにも関わらず連日同じ注射オーダーがされ、使用されないまま返品されるという無限ループが続き、関連職種への負担も大きい。またオーダーがない注射やICU内の在庫を抱えていない注射に関しては、他患者の注射を借用することもあり、インシデントやアクシデントにつながる恐れもある。注射オーダーの適正化を図ることで、注射に要する時間や業務の無駄を軽減できると考えたため。 | ||
| 9 | 臨床工学部 | 病棟循環型貸出システムの改善~輸液ポンプの効率運用・貸出庫のゼロからの脱却~ | 優秀賞 |
| sMilE2640 | 現在、臨床工学部での中央貸出機器(約2300台)には多数の輸液ポンプ(約700台)があるが、病棟での実際の需要に対して貸出可能な台数が不足している。特に必要な輸液ポンプが貸し出せず、在庫の問い合わせが増加している。このままでは新しい輸液ポンプを購入する必要がある。この状況を改善し、患者様に迅速な治療を提供するため、貸出システムを見直し、効率的な利用を目指す。 | ||
| 10 | H2救急、E4救急・HCU | 救急病床での受け入れ体制の改善 | |
| 救急病棟24時~後編~ | 入院時に行う業務が多かったり入院が重なることで入院受けに時間を要することがあり、入院説明等で看護師が患者の側から離れる時間が生じて、結果的に記録や処置に時間を要することがある。そのため①入院時の業務を減らす②入院後の説明にかかる時間を短縮する。この2点を取り組むことで入院受けの時間を短縮させることで患者は早く治療を受けることができ患者ファーストの目標に近づけるのではないかと考えたため。入院の説明を簡略化することは過去のTQM活動でも取り組んでおり、活用できる事をシステム化し定着させる事で、入院時のデータベースを行う時間を削減できないかと考えた。 | ||
| 11 | 中央放射線部 | 放射線治療計画業務の効率化を図りたい | |
| それいけ!Radiation Therapy House | 現在、放射線治療の1日の新患は3〜4人程度である。放射線治療計画立案までに、放射線技師は放射線治療計画用のCT撮影後、放射線治療計画装置でCT画像の取込を行い、体内臓器の輪郭抽出(以下コンツーリング)を行っている。それらが終了後に放射線治療医へ、放射線治療計画の作成を依頼している。放射線治療計画装置に関する業務量は大きく、TQM活動を通じて作業内容・流れの見直しを行い、放射線治療計画装置に関する業務の効率化を図る。 | ||
| 12 | 薬剤部 | 調剤業務の効率化と負担軽減 | 優秀賞 |
| 業務の鉄人 | 近年、全国的に病院薬剤師は不足しており、当院も例外ではない。さらに、当院の院外処方率は10%程度であり、薬剤部は外来と入院の調剤業務に追われる毎日である。アフターコロナの現在、処方量の増加も相まって、業務終了後のスタッフの表情や言動からは、強い疲労感が垣間見える。現状を打破し、明るく楽しい薬剤部を創るための足がかりとして、調剤業務を効率化し負担を軽減するべく、今回のテーマを選定した。 | ||
| 13 | 中央検査部 | 外来採血における患者待ち時間の短縮 | 最優秀賞 お客様賞 |
| WBC (Waiting Buster's Circle) -諦めるのをやめましょう- |
12C採血室では毎日平均500人程の外来患者の採血業務を行っている。現在、採血での患者待ち時間はシステムが導入され短縮はされているが、日によって突発的に長い待ち時間が発生する場合があり、そのことにより待合室が座れないほど混雑してしまうという状況がしばしば発生している。 採血は外来患者にとって最初の待ち時間となる可能性が高く、ここをスムーズにすることは患者経験価値の向上に繋がると考え、このテーマを選定した。 | ||
| 14 | 北第五病棟 | 患児の入院中の過ごし方について | |
| それいけ!Children ~遊んで、学んで、 元気100倍!!~ |
小児にとって遊びや学習は発達に欠かせないものであるが、院内学級やプレイルームの利用方法が明確でないために、入院中ゲームやスマホばかりして過ごしている。入院すると生活リズムの乱れがでてくるため、学校に行きづらくなるなど家族より心配の声が挙がっている。重症心身障害児も学習を受ける権利があるのにも関わらず、寝たきりで過ごすことが多く、家族より他の患児と同じように学習や遊びを取り入れて欲しいと要望があった。 | ||
| 15 | 14A | 緊急カテーテル検査の業務を整理して、患者を安心・安全・迅速に搬入することができる | |
| 冬になったら | 循環器外来では、緊急カテーテル治療となるケースがある。 その際、搬入に関する業務チェックリストはあるが行うべき業務や引継ぎ事項の決まりがない為、確認作業により業務が中断している。また、他職種間で情報共有できていないこともあり時間のロスも発生している。そこで、迅速かつ安全にカテ室へ搬入ができることで、患者にも安心感を与えられるような取り組みを行いたいと考えた。 | ||
| 16 | 東第五病棟 | 夜勤の業務整理を行い、夜勤者の超過労働時間をなくしたい | |
| 早く出勤するの なぁぜなぁぜ? ~業務スッキリ~ |
夜勤の勤務時間は約14時間でかつ受け持つ患者数も日勤に比べて多く、精神的・肉体的に負担が大きい。始業開始前から出勤し超過労働を行うスタッフがいる。その理由を調査した結果、消灯前までに業務を終わらせたい、不安なので早めにでてきている、術後やせん妄患者さんの対応など業務などで業務が終わらないため、早く出勤していることがわかった。業務を見直すことで夜勤者の超過労働時間をなくしたい。 | ||
| 17 | 中央第三病棟 | 整形外科病棟における術後腓骨神経麻痺を0(ゼロ)にする | 審査員特別賞 |
| チームコツコツ ~ダメ。ゼッタイ。 腓骨神経麻痺~ |
現在整形外科病棟では、腓骨神経麻痺予防として腓骨小頭の除圧を行っているが、体位保持用の枕のサイズは様々であり、数にも制限があり、経験年数や職種などによっても除圧方法に差がある。術後腓骨神経麻痺を起こすと、下垂足となり、障害が残る可能性がある。患者は疼痛を軽減させよりよいADL獲得のため入院し手術を行うが、腓骨神経麻痺により障害を生じ、歩行障害を起こすと、患者の望む姿とはほど遠く、患者の希望に反してしまう。そのため、今回のTQM活動にて術後腓骨神経麻痺予防方法を考え、整形外科病棟における腓骨神経麻痺を無くしたいためこのテーマにした。 | ||
| 18 | リハビリテーション部 | 業務のムダをなくし、セラピストの負担軽減 | |
| タイムバスターズ(R) | 患者へのリハビリ介入以外の業務(病棟移動、カルテからの情報収集・カルテ記載、計画書説明、処方せんの修正など)に費やす時間が多いことから、始業前出勤や昼休みなど就業時間外に業務を行っている現状がある。この為、上述の業務実態を把握して見直し、時間外業務の削減を図ることで、職員の負担軽減を目指したい。 |
| No | 部署 | テーマ | 受賞 |
| サークル名 | テーマ選定理由 | ||
| 1 | 北第八病棟 | 処方薬が患者に届くまでの手間を見直し、ムダの削減につなげる | |
| お薬もう届いてるってコト?! | 当日処方薬オーダーには鎮痛剤や届き次第開始など急ぎの指示がある。しかし定期メッセンジャー配送時間とタイミングが合わない場合、病棟に届くまでに時間を要すため治療開始が遅延することがある。処方薬搬送⼯程にかかわる看護師やコメディカルの業務に着目し、ムダの削減と効率を図ることでタイムリーに処方薬が届き、患者の治療に早期介⼊できるよう活動したい。 | ||
| 2 | 医療福祉室 | 地域からの情報を無駄にしない | |
| 二代目 医療福祉侍 | 医療福祉室は飯塚病院における地域との連携窓口の役割を担っており、⼊院時にはケアマネージャーや施設などから患者の⼊院前の生活に関する情報を受け取ることが多い。しかし受け取った情報が十分に活かされていないように感じており、地域から届いた情報を無駄にせず、有効に活用できるようにしたい。 | ||
| 3 | 14B (内視鏡センター) |
検査待ち時間を減らしたい | 最優秀賞 お客様賞 |
| 待っちょ時間を なくしマッスル |
内視鏡センターでは、1日に約70件の検査を⾏っており、1検査あたり30分毎で検査枠をとっている。その枠の中で患者⼊替え作業も⾏っており、特殊な検査や処置を⾏う際は、30分の枠に収まらない。それにより、その後に続く検査の予約時間に患者を⼊室させることができない為、待ち時間が発生してしまう。今回、検査予約時間に患者を⼊室させることにより、患者待ち時間を削減したいと考え、このテーマに選定した。 | ||
| 4 | 東第六病棟 | リハビリスタッフと連携し、退院へ向けた日常生活の継続支援 | |
| カンジャニ∞エール | 東6階病棟では機能障害により日常生活に介助を要する患者が多い。また、それに対するケアの方法がスタッフ間で統一出来ていない問題点がある。機能回復のためにはリハビリ・病棟スタッフの連携が必要と考えた。そこで、⼊院時から退院までのリハビリ・看護介⼊を把握し、患者にとっての最適なタイミングや環境を整え、退院へ向けた日常生活の継続⽀援ができるようなしくみづくりをしていきたい。 | ||
| 5 | 地域包括ケア推進本部 | 職員が仕事と家族介護の両立をできるように支援する | 審査員特別賞 |
| 介護ほけんの窓口 | 当部では現在患者に介護保険の相談⽀援を⾏っているが、職員の家族介護の相談は積極的に⾏っていない。今回職員を対象に家族介護の困り事の有無を調査した結果、「現在困っている」「将来困りそうである」と回答した人は62%と、何かしら困っている職員が多い事がわかった。このため現状の職員のニーズと課題を明らかにし、それに対応する新たなサービスを構築することで、職員が安心して仕事に従事できる環境づくりに貢献したい。 | ||
| 6 | 中央放射線部 | ポータブル撮影業務の効率化 | |
| ポータブル X-Press | 朝早めや急ぎのポータブル撮影依頼が多いため、多数のスタッフが同時にポータブル業務に就く必要がある。その結果、他の業務への対応人数が手薄となり患者待ち時間の増加に繋がっている。ポータブル撮影業務の効率化を図ることで、①ポータブル撮影時の被験者の待ち時間の短縮②一般撮影業務の待ち時間の短縮③緊急性が高いものほど優先的に撮影可能④放射線部スタッフの負担軽減などの効果が期待される。 | ||
| 7 | NICU・GCU | 入院オリエンテーションの内容と方法の見直し | 優秀賞 |
| Nっ子ふぁみりー | NICUでは、⼊院オリエンテーションを家族へ⾏う。しかし、スタッフにより、説明項目や時間にバラツキがみられることから、家族間での理解に相違があり、何度も同じ内容を説明している現状にある。今回、⼊院オリエンテーションの内容と方法を⾒直すことで、重複説明をなくし、家族へタイムリーな⼊院オリエンテーションを⾏いたいと考え、このテーマにした。 | ||
| 8 | 医事課 | 患者さまへ入金機(自動支払機)利用の推進 | |
| 入金機kids | 外来患者さまの診療費のお⽀払い方法は、⼊⾦機もしくは医事課スタッフが対応する会計窓口でのお⽀払いです。現状は、⼊⾦機で⽀払い可能な患者さまが会計窓口に並び、諸事情により会計窓口でのみ⽀払い可能な患者さまが⼊⾦機に並ぶこともあり、⼊⾦機が利用されていない状況です。そのため、⼊⾦機の利用を推進したいと考え、このテーマを取り上げました。 | ||
| 9 | 東第四病棟 | タイムリーな指示出し・指示受けを目指す | |
| SHOKAKI×FAMILY | 東4階では1ヶ⽉に⼊院転⼊平均約125件、内視鏡約60件⾏っている。内視鏡中や外来中に看護師より指示確認の電話があるため医師の手が止まり患者を待たせることがある。電話件数を少なくすることで内視鏡中の医師の手を止めず患者の安全性を保てる。看護師は電話でスタッフステーションに⾏く無駄な動きが無くなる。タイムリーな指示出し、指示受けの仕組み作りを⾏うことで患者と関わる時間を確保したいと考えこのテーマとした。 | ||
| 10 | 南3B病棟 | 患者の価値を最大化するための効率的なHOT指導 | |
| HOT指導の二刀流 It's sho-time! |
南3B病棟は呼吸器病棟でありHOT導⼊患者が多い。症状再燃による緊急⼊院を予防するために導⼊前の患者指導が重要である。統一した指導を実施するためにフローを作成しているが、指導時間の捻出に苦慮しており、指導する側の⼒量の差が生じている現状がある。指導側の質を担保すると同時に、患者主体の指導を実施し、効率的・かつ効果的な指導を実施する事で、不要な⼊院を予防し患者のQOLを維持出来るような取り組みをしたい。 | ||
| 11 | リハビリテーション部 | 必要度の高い患者さんのリハビリ介入時間を確保したい | 優秀賞 |
| リハ時間を生成せよ!!リハコンドリア!! | これまでのTQMで、担当が休みの際に必要度の高い患者を明確にするため、優先度の基準等を導⼊してきた。しかし、疾患別グループによって担当患者数や代⾏履⾏数に偏りがあり、必要度の高い患者さんのリハビリ時間を十分に確保できないことがある。この問題を解決することで、必要度の高い患者さんのリハビリ介⼊時間を確保できる。 | ||
| 12 | 薬剤部 | 薬剤部業務の効率化を図り、患者待ち時間を短縮する | 最優秀賞 お客様賞 |
| 業務の鉄人 | 薬剤部では、一日平均700枚の外来処方箋を院内で調剤している。患者サービス向上のために待ち時間の短縮は常に課題であり、これまでも様々な⼯夫を⾏ってきた。しかし現在でも平均待ち時間が30分を超える時間帯が毎日発生している。今回、これまでも⼯夫を重ねてきた調剤業務をさらに⾒直し、効率化を図ることにより患者待ち時間を短縮させたいと考え本テーマを選定した。 | ||
| 13 | 南2A病棟 | 入院患者の内服に関する業務改善 | |
| 時間内 ないふくッキング | 現在、病棟内で内服薬を看護師管理している患者が48名中35名いる。その内服薬はすべて看護師が内服ボックスにセットし、別の看護師がダブルチェックを⾏っている。また、事前に処方があればその場で内服セット可能だが、内服セット当日に処方がないことや、16時以降に内服の変更や中止の指示がでることがある。これにより次勤務者へ内服セットを引き継ぐことになるため、次勤務者の負担となることや内服セット間違いに繋がる可能性がでてくる。そのため、内服に関する業務の改善に努めたい。 | ||
| 14 | 中央第四病棟 | 心臓カテーテル検査オリエンテーションの充実 | 審査員特別賞 |
| カテ室の知らない世界 | 中央4階病棟は、循環器科内科病棟で心臓カテ-テル室が併設されており、年間約2,500例(緊急カテーテル検査を除く)の心臓カテーテル治療・検査や不整脈治療が⾏われている。担当看護師は「カテーテルオリエンテーション」をカテ-テル前に⾏っているが、患者へ、病棟で作成した説明用紙を用いているにも関らず、看護師によってその説明内容、説明の仕方や説明時間にバラツキがあると多くのスタッフが感じている。その結果は、患者さんの理解度等にも影響を与えている可能性も否定できない。そこで、今回のTQM活動では、カテーテルオリエンテーションの実態について現状を知り、バラツキが生じている要因(原因)を突き止め、それに合った対策を実施することで問題の根本的解決を図りたい! | ||
| 15 | 北第七病棟 | 処置箋入力漏れの削減 | |
| 処置箋忘れたら しょーちせん!! |
処置箋は、採⾎や画像検査のように事前にオーダーできない項目で、看護師等が実施した処置を診療報酬に繋げる為の重要なツールである。北7階病棟では、処置箋勉強会の実施や定期的に処置箋⼊⼒漏れ調査を実施し、スタッフへ周知しているが明確な削減には⾄っていない。処置箋⼊⼒漏れの要因を分析し、処置箋⼊⼒にかかる時間や⼊⼒漏れを確認する作業を削減し、患者対応の時間増加、診療報酬の適正請求へ繋げていきたい。 | ||
| 16 | 小児センター・ 北第五病棟・NICU 医療福祉室・改善推進本部 |
医療的ケア児に支給する在宅医療物品の適正量を把握、決定する | |
| iCARE パート2 (良いケア 医療的ケア児) |
医療的ケア児で在宅医療物品を必要とする患者は36名おり、外来では毎⽉在宅医療物品を患者毎に準備をしている。医療評価⼊院や体調不良で⼊院する際に、在宅医療物品は当院⽀給である。退院後も家族より請求があれば⼊院していた⽉の在宅医療物品を⽀給している現状があるが「⾃宅にたくさん物品がある」という意⾒があった。患者の中で在宅医療物品を⽀給する量にばらつきがあり、現在の量で⾜りているのかどうか、⽀給量が適正であるのか評価が必要であると考えた。 |