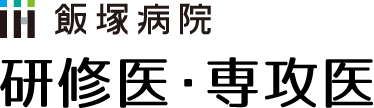先輩の声
上杉 優佳
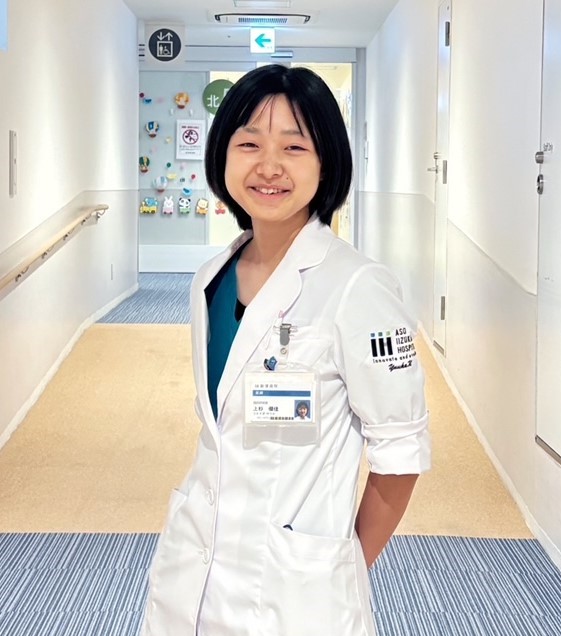
私は生まれも育ちも東京ですが、一度都会を離れた場所で医療を見てみたい、また誰も知り合いのいない環境で挑戦してみたい、という思いから飯塚病院を志望しました。見学で感じた先生方の教育への熱意、研修医同士の活発な学び合いの雰囲気に惹かれ、ここでの研修を決めました。
研修が始まると、毎日が新しい発見と学びの連続でした。忙しい救急外来や病棟業務の合間で、上級医の先生方は常に『なぜそう考えるのか』『次に何を確認するか』考えるよう指導いただき、単なる知識の伝達ではなく、理論的に考えて説明する習慣をつけることができたと感じます。特に印象に残っているのは、研修医同士の学びの文化です。救急症例を翌朝共有し、自然にディスカッションが始まる―そんな風景が日常でした。互いの専門や興味が異なっても、飯塚に根付く『shareの精神』のもと、切磋琢磨できる仲間に支えられてきました。研修が忙しい時期でも『楽しく学ぶ』という感覚を忘れずにいられたのは、研修医の先輩後輩、同期の存在が非常に大きかったと感じています。
研修生活では看護師や薬剤師、検査技師、ソーシャルワーカーなど、他職種の方々と連携する機会も多く、自分の視点だけでは見えないことに何度も気づかされました。手技やデータの見方を看護師・検査技師の方から教えていただいたり、看護師から医学的な質問をされてタジタジになったりすることもあり、医師に限らない病院職員皆さんに支えられてきたことを痛感しています。医療は決して一人では成り立たないですし、職種を超えてスムーズなコミュニケーションを取ることの重要さを学ぶこともできました。
飯塚病院は筑豊地域唯一の三次救急病院であり、多様な背景をもつ患者さんがいらっしゃいます。経済的に困窮する若い女性、身寄りのない高齢男性など、病気だけでなく患者さんとその家族の人生そのものと向き合う機会が多くありました。
そのなかで私が強く感じたのは、治療方針の正しさと同時に、患者さんと家族が納得できるかどうかを大切にする医療の必要性でした。医学的介入を最大限求める患者さんもいれば、できるだけ薬は少なく早く家に帰ることを望む患者さんもいて、医療へのアクセスが非常に良い日本だからこそ、できる医療の押し売りになってはいけないということを常に意識する必要があると思います。地域医療や訪問診療などでは、患者さんの自宅・施設での生活に触れる機会が多く、病院がいかに患者さんにとっての非日常であるかを忘れてはいけないと感じました。治療をしたい思いと生活を維持したい気持ち、家族の思いも交差する中で、医師として家族との信頼関係を築きながら、その人らしい生き方を支える、という医療を勉強することができました。
日本は世界有数の高齢化社会ですが、同時に皆保険制度を実現している数少ない国でもあります。高齢化社会のように『最先端を提供するだけが治療ではない』という制約の中で、いかに患者さんと家族の納得できる医療を提供していくかは、日本の現場の医療者が世界に先駆けて挑戦している分野であると感じています。これから専攻医として新たな道を進みますが、飯塚で得た学びあいの精神を胸に、医学知識に対して貪欲に、目の前の患者さんの生き方に誠実に向き合い続けていきたいと思います。